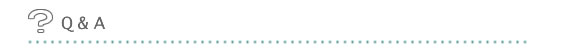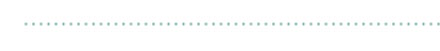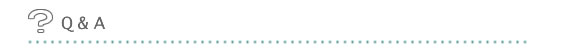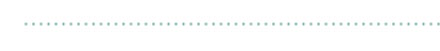1.   |
介護保険を利用できるのはどのような人ですか? |
|
  |
介護保険とは被保険者(加入者)となって保険料を負担し介護が必要と認定された時には費用の1割を支払って介護サービスを利用する仕組みです。
介護保険は日本国内の40歳以上のすべての国民が利用可能です。ただし、64歳までは以下の16種類の特定疾病の方が対象になります。
●がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
●関節リウマチ ●筋萎縮性側索硬化症
●後縦靭帯骨化症 ●骨折を伴う骨粗しょう症 ●初老期における認知症
●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
●脊髄小脳変性症 ●脊柱管狭窄症 ●早老症 ●多系統萎縮症
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ●脳血管疾患
●閉塞性動脈硬化症 ●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
ページのトップへ▲ |
|
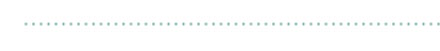 |
2.   |
要介護認定の申請はどこにすればいいのですか? |
|
  |
練馬区では、本人または家族などが高齢者相談センター・同支所または介護保険課に申請します。
ヘルプメイトのケア・マネジャーが、申請手続きの代行も承っております。 |
ページのトップへ▲ |
|
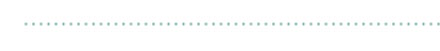 |
3.   |
ケア・マネジャーとは何ですか? |
|
  |
公的資格の一つで、介護支援専門員(ケア・マネジャー)は、お客様の意向にそって介護保険の限度額の中で、生活のスタイル、家族の状況、住
まいや地域のサービスの状況を考慮し、1人ひとりにあった「ケアプラン」を作成し各種の介護サービス導入の援助を行います。
また日頃の介護サービスに関する、ご質問、ケアプランの変更等の相談にも応じています。 |
ページのトップへ▲ |
|
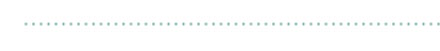 |
4.   |
申請後、認定結果が通知されるまでの間でも介護サービスを利用できますか?
|
|
  |
はい。申請後、認定結果が通知されるまでの間でも、「暫定ケアプラン」を作成して届けを出すことで、1割の自己負担で介護サービスを利用できます。
ただし、認定の結果「非該当(自立)」となった場合は、全額自己負担となります。 |
ページのトップへ▲ |
|
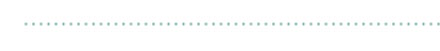 |
5.   |
要介護認定の有効期間内に、心身の状態が変化した場合はどうなるのでしょう?
|
|
  |
有効期間内に心身の状態が大きく変化し、認定された要介護度に当てはまらなくなったときには、高齢者相談センター・同支所または介護保険課に区分変更の申請をしてください。手続きの方法は、初回と同じです。 |
ページのトップへ▲ |
|
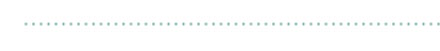 |
6.   |
介護サービスを利用したとき、費用の負担はどうなりますか? |
|
  |
ケアプランに基づいてサービスを利用するとき、みなさんがサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割で
す。ただし、利用するサービスによっては、別に食費・居住費(滞在費)や日常生活費などが必要となる場合や、介護保険の
対象とならないサービス費用もあります。なお、ケア・マネジャーなどが行うケアプラン作成などの費用は、全額介護保険から
支払われ、自己負担はありません。
ただし、介護保険では、要介護度(要支援1・2、要介護1~5)に応じて、利用できるサービス費用の上限(利用限度額)が決
められています。上限の範囲内でサービスを利用する際の自己負担は1割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合、超え
た分は全額利用者の負担となります。 |
ページのトップへ▲ |
|
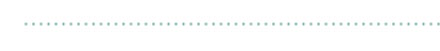 |